メディカルアフェアーズ情報
メディカルアフェアーズの最新情報を更新していきます。
-
コラム
Patient Journeyを描く際のTips
 コラム2024.03.04 (Mon)2024.03.04 (Mon)
コラム2024.03.04 (Mon)2024.03.04 (Mon)Patient Journeyを描く際のTips
つい先日、私は、「Emotional journey of patients with specified intractable diseases in Japan」という論文を発表しました。2024年3月1日現在は、速報でインフォーメーションされています。(リンク) この論文は、難病の患者さんを対象に確定診断遅延に関わるアンメットニーズを探るために、患者さんのEmotion(感情)の状態を明らかにし、かつ、それを定量的に示したものです。感情の状態が最も低くなるところにこそ患者さんのアンメットニーズが存在している可能性が高いことを私は常に提唱してきましたが、この研究はその一つの例となります。 また、当該研究は、限られた数の患者さんへのインタビューではなく、比較的多くの患者さんを対象としたアンケート調査によって、「感情の状態」を捉えた研究です。 -
コラム
患者団体との協働について
 コラム2023.07.07 (Fri)2023.07.07 (Fri)
コラム2023.07.07 (Fri)2023.07.07 (Fri)患者団体との協働について
2023年1月23日のコラム「Patient Centricityとは何なのか?」でも述べました通り、製薬企業をはじめとした多くのヘルスケア関連企業が、Patient Centricityという言葉を掲げていますが、その活動の1つとして、患者団体との協働があります。当社としても、企業と患者代表が医療上の問題について議論し、共に解決に向けた取り組みをすることは、望ましい社会の在り方だと考えます。その一方で、両者の関係が不健全なものにならないよう、利益相反には常に気を配らなければなりません。例えば製薬企業の場合、日本製薬工業協会(製薬協)が、「患者団体との協働に関するガイドライン」1を出しています。当社は製薬企業でございませんが、上記のガイドラインを参考にして活動しています。あくまで患者の利益を重視し、公正な立場で関わっております。 最近の活動をご紹介しますと、全国膠原病友の会様と共同で医療講演会を実施しました(2023年5月11日「正しく学ぼう!膠原病の最新治療」2)。この講演を実施するにあたり、理事の方と定期的に会議を開きましたし、企画にあたっては会員の方から意見も募りました。講演会のコンセプトについては当該団体の意思を尊重し、私たちは会を進行する上で必要な助言をするにとどめました。当社は医薬品等を製造販売しているわけではありませんので、利益相反が生じず、お互い公正な立場でやり取りができたと感じています。 -
コラム
患者サポートプログラム 事例紹介2~医療機関とのコミュニケーションサポート~
 コラム2023.06.16 (Fri)2023.06.16 (Fri)
コラム2023.06.16 (Fri)2023.06.16 (Fri)患者サポートプログラム 事例紹介2~医療機関とのコミュニケーションサポート~
今回は副作用の症状を自覚しながら受診時に医師に報告を躊躇うBさんの事例です。半年前に○○癌と診断され、大学病院に通院しています。診断後すぐに治療が開始されました。幸い、早期発見のため薬物療法から開始することとなり、患者サポートプログラム(PSP)対象の薬剤が処方されたため医療機関からプログラムを紹介されすぐに登録となりました。 PSP看護師が、定期的に状況を伺うお電話を行い、注意して欲しい症状(△△)について毎回話をしておりました。△△が出てきた場合や少しでも症状が悪化していると感じた際にはすぐに医療機関に電話し、指示を仰ぐように依頼していましたので、△△について注意すべきとの自覚がありました。(個人差はありますが、△△は早期に対応すれば薬剤を中止せず減量等で継続できます。) あるコール時にいつものように様子を伺うと、前日から△△らしきものがあると話をされました。担当のPSP看護師が様子を聞き、医療機関に電話して指示を仰ぐように伝えたところ「この症状を伝えたら薬剤中止になるのでしょうか?」とのコメントがありました。話を伺うと、せっかく薬剤の効果も見られてきたため、中止したくない。治療を開始して日常生活への影響もほとんどなく、注意すべき症状は我慢できるから報告しない方が良いと思っているとのこと。更に、他剤に変更となると、対応できる薬剤が減っていく可能性も考え、なるべく長い期間同じ薬剤で頑張りたいとの意向がある状況でした。気持ちはよくわかります。数字的な効果も表れ、前回の受診時には医師から「効果が確認できますね。○○さんに合っているみたいなので、このまま続けましょう。」と言われていたら、多少辛くてもこのまま続けるのが一番良い!と考えてしまうのですね。 看護師は添付文書上も“適宜減量”の記載もあり必ずしも中止になるとは限らないこと、早期に対応することが一番重要であることを伝え、医療機関への報告と今後の指示を仰ぐよう依頼しました。加えて、Bさんが薬剤を継続したいと思っていることを伝えても全く問題ないことと、医師はBさんの意向も踏まえ、他の検査値等の状況を加味して指示することになると考えられることを伝えました。その後、Bさんは医療機関に電話し、受診日変更と受診日までの薬剤の指示がなされました。薬剤は減量して継続となり、△△の症状改善の薬も処方され、△△はほぼ改善された状況となりました。 この件の後も看護師からの定期コールは続いており、薬の効果を実感しながら前向きに治療を継続している様子を確認しています。薬剤中止になった場合にはPSPのサービス提供も基本的に中止となりますが、そのような場合でも的確な治療を医師が選んでいること、薬が合致するか確認する期間が必要とされることもあること、患者さんの意思を医師に伝えることはとても重要であることを伝え、その後の治療も前向きに受けていただけるような会話で終了する形を心がけております。 患者さんの意思を医師に伝えながら治療できるようにサポートする事例紹介でしたが、いかがでしたでしょうか? 当社PSPメンバーでも、いざ自分が患者となり受診すると、あれを伝えればよかったとか、これを聞いてみればよかったと振り返ることあるよね、と話をすることもあります。同じような経験をしたことがある方は多いと思います。そのような時にPSPを活用いただけると感じております。 クライアントの方の意向で、一人の患者さんに対し、無期限(プログラム自体が終了するまで)でフォローするケースや一定期間のフォローとなるケースなど様々です。いずれの場合にも弊社ではインバウンドコールはいつでも(含:一定期間終了後)引き受ける形のプログラムで運営しております。患者さん/ご家族に対し、同じ看護師が継続して対応することで、ちょっとしたことを確認する時にも連絡しやすい環境を整えております。ご興味ある方はお気軽にお問い合わせください。 お問い合わせ -
コラム
患者サポートプログラム 事例紹介1~緊急時のお問い合わせ~
 コラム2023.02.21 (Tue)2023.02.21 (Tue)
コラム2023.02.21 (Tue)2023.02.21 (Tue)患者サポートプログラム 事例紹介1~緊急時のお問い合わせ~
最初の紹介は発作で死に至る可能性のある希少疾患に罹患しているAさんの事例です。約2年前に診断され、大学病院に通院しています。診断までに数年かかりましたが、診断後は定期的に通院し、担当医師との関係は良好です。患者サポートプログラム(PSP)は、先生から紹介されたのでとりあえず登録してみたという状況であり、特に質問したい内容や具体的なサポ―ト依頼はありませんでした。 定期的な電話連絡を通じ、日常生活のことなどを伺いながら適宜情報提供を行っておりました。ところが、ある予約日に連絡がとれず、担当看護師が後日お話を伺ったところ、予約日に緊急受診をしていたとのことでした。詳しく伺うと、希少疾患を診てもらうために通院している大学病院は自宅から遠いため、近くの病院に緊急受診をしていたのですが、その病院ではAさんが罹患している希少疾患についてどのように対応したらよいのかわからず、疾患の治療薬もなかったためにそのまま様子をみるだけの状況だったとのことでした。幸いなことに、様子をみるだけで症状は落ち着き、数時間後にご自宅に帰られたそうです。この経験から、次回以降、緊急時には大学病院まで行かなければならない、と不安に感じていると仰っていました。担当看護師から、これまで大学病院の担当の先生と緊急時対応について話し合いを行ったことがあるのか伺ったところ、話し合ったことがないとのことだったため、次回受診時に確認することを促しました。患者さん自身、緊急時には大学病院に行くべきであり、対応について担当医に相談すべきではないと思っていた様子がありました。その後、患者さんより、受診時に確認でき、近くの病院でも緊急時に対応できるよう対策がされたとのお話がありました。その際の患者さんとの会話から、担当看護師は、患者さんが担当医に質問できたことで治療に対する主体性が向上した様子があると感じています。 ここまでお読みいただきありがとうございます。「えっ、それだけ?」「緊急時の対策ができただけじゃないか?」と思われた方も多いのではないでしょうか?緊急時の確認と聞くと当たり前のように感じると思いますが、緊急時の確認はあくまで一例であり、些細なことでも確認ができていないこと、担当医に聞くことを躊躇していることが意外にあることがわかってきました。そのような中で、病院に勤務していた看護師から、「先生に聞いてみたらどうでしょうか?」「先生に確認した方がいいですよ」と言った一言で患者さんが前に進めたケースは多くあります。希少疾患であれば、この疾患を診てくれる先生は多くないから、先生に嫌がられないか、といったことを気にされる方もいらっしゃいます。希少疾患でなくとも、先生に聞いたら嫌がられないかと躊躇して聞かないことで、結果としてずっと不安を抱えた状況になります。PSPを通じて、そっと患者さんの背中を押すことで、治療に対する主体性を高めることができると感じています。 次回は、患者さんへの疾患・薬剤の情報提供を行った事例紹介を行う予定です。 当社PSPに関してご相談やご質問等ございましたら、いつでもお気軽にご相談くださいませ。 お問い合わせ -
コラム
Patient Centricityとは何なのか?
 コラム2023.01.13 (Fri)2023.01.13 (Fri)
コラム2023.01.13 (Fri)2023.01.13 (Fri)Patient Centricityとは何なのか?
まず、製薬業界全体が、Patient Centricityを掲げるようになった背景について考察したいと思います。色々なところで言われることですが、近年、医薬品の開発パイプラインが変化していますⅰ)。かつては、生活習慣病のような、患者が多数存在する疾患に対して、新たな医薬品が次々と開発されていました。当時、一人一人の患者の声を聴くよりも、処方権を持つ医師から「感触」や「使い勝手」を聴取することが、重視されてきたことは否定できないでしょう。確かに、そちらの方が効率は良いでしょうし、実際に、それによって多大な利益を得てきました。しかし現在では、このようなやり方だけでは思うような利益を得られなくなった、というのはよく耳にするところです。 それと同時に、最近は、より希少な疾患に焦点を当てた医薬品開発が活発になっています。希少疾患の場合、患者数は少ないですが、その分、治療薬の薬価が高い傾向にあります。そのような環境では、患者一人のことを深く知ることが、今まで以上に価値をもつという側面があります。 患者と医師の関係性の変化も、影響を与えていると考えられます。近年、古典的なパターナリズムを目にする機会は減り、患者が自分の治療について意見を述べ、意思を決定していく場面が増えています(もちろん、十分できているとは言えないかもしれません)ⅱ)。そのような環境では、患者が疾患や治療に対して、適切に理解をすることが不可欠です。医療・科学の不確実性を伝えつつ、正確な医療情報を理解しやすい形で提供することが、より一層求められます。 -
コラム
Creating Shared Value(CSV)とは
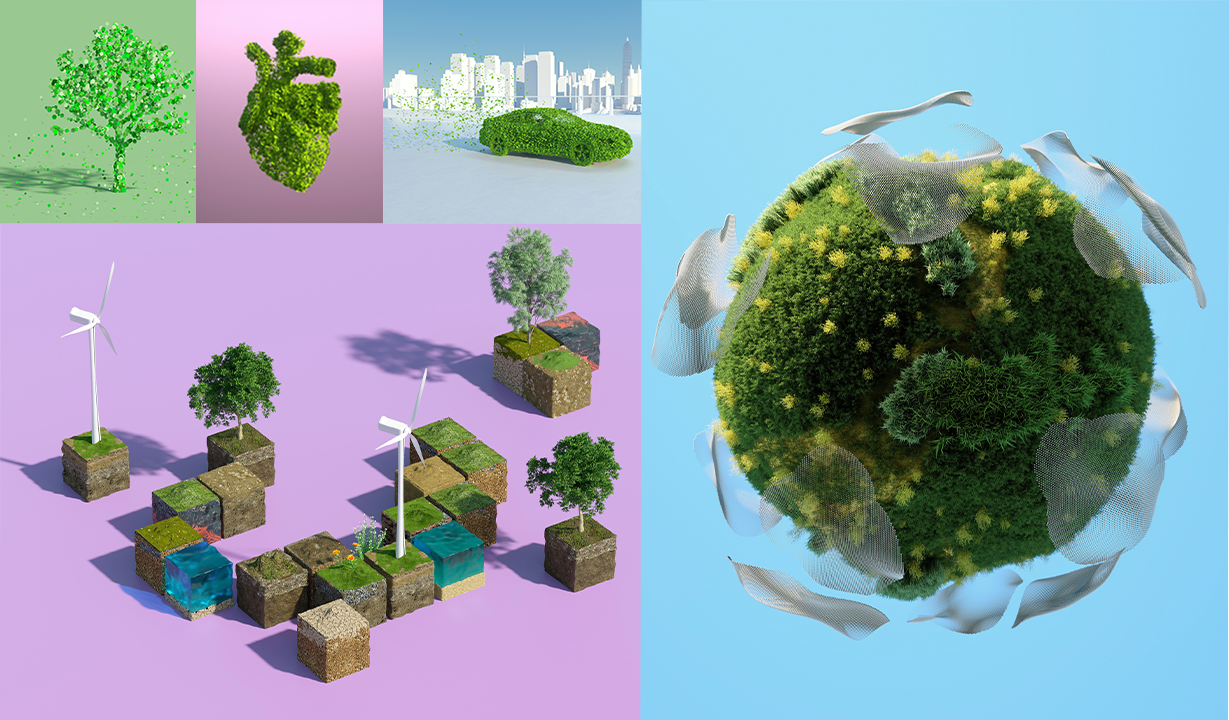 コラム2022.12.22 (Thu)2022.12.22 (Thu)
コラム2022.12.22 (Thu)2022.12.22 (Thu)Creating Shared Value(CSV)とは
近年、製薬企業はPatient Centricityを掲げ、患者中心の活動を行うということを業界全体としても明言しています。この流れは、アメリカマーケティング協会によるMarketing 1.0のProduct-drivenからMarketing 2.0のcustomer-orientedを経てMarketing 3.0のHuman-centricに移行したⅰ)ことと考え方が近く、企業の考え方がこのように変化してくるのは自然のことであると考えても良いかもしれません。 -
コラム
患者サポートプログラム(Patient Support Program)とは
 コラム2022.11.21 (Mon)2022.11.21 (Mon)
コラム2022.11.21 (Mon)2022.11.21 (Mon)患者サポートプログラム(Patient Support Program)とは
近年の環境変化の中で、各製薬会社は「Patient Centricity」の活動を活発化しています。どの部署に所属していても、「Patient Centricity」を基に、様々な戦略・施策が検討され、常に患者さんを中心に議論されることが求められています。 そのような流れから、直接、患者さんをサポートする様々なプログラムが提供されてきています。当社においても、コンサルティングを行う中やMAアカデミーの講義の中で「患者サポートプログラムとは具体的に何をしたらいいのですか?」「患者サポートプログラムの効果検証が難しいのですが」「○○を行ったけれど、患者さんからの評価はあまりよくなかったのですが」と言った声を聴くことが増えてきました。 患者さんをサポートするプログラムは、Patient Support Program(PSP)と呼ばれますが、PSPには様々な形態があります。服用管理のアプリの普及もさかんですよね。これまで医療機関経由で入手していた各疾患・薬剤の資料「患者さん向け資材」を郵送してくれるサービス、SNSや電話を通じて直接話をするサポート、薬剤を個宅配送するサービス検討も増えてきています。 ではなぜPSPがさかんになってきたのでしょうか?これまで製薬企業は主に医療機関から患者さんの情報を入手していました。しかし医療機関側でも患者さんの状況を全て把握することは難しい状況です。患者さんも「何か対応してもらいたいほど困っていない」「忙しそうに仕事されているからあまり余計なことは言わないようにしよう」「我慢できるから受診は次回の予約まで待とう」と考えることは容易に想像できると思います。これらが結果として“医療のムダ”に繋がっている可能性があります。適切なタイミングで介入し、治療からの脱落を防ぎ、治療効果の最大化や医療資源の有効活用に繋げるためにPSPがさかんになったと考えられます。 当社では主に電話での会話を通してPSPを実施しています。“MSL(メディカルサイエンスリエゾン)の役割とその活動の重要性とは” でも紹介しているインサイト収集ですが、当社PSPでは患者さんのインサイトを収集しています。会話を通じて、何となく感じていたことを患者さん自身も認識するようになることも多々ありますが、このインサイト収集は本当に一筋縄ではいかないです。 次回以降、PSPを通じてどのような行動変容があったか等をご紹介していきたいと思います。 当社PSPに関してご相談やご質問等ございましたら、いつでもお気軽にご相談くださいませ。 お問い合わせ -
コラム
メディカルアフェアーズ部に所属して仕事をするには?
 コラム2022.10.03 (Mon)2022.10.03 (Mon)
コラム2022.10.03 (Mon)2022.10.03 (Mon)メディカルアフェアーズ部に所属して仕事をするには?
MAでは様々な業務が行われており、それぞれの業務に高い専門性を必要としています。特にMSL(メディカルサイエンスリエゾン)においては、社外医科学専門家(STL)との医学的・科学的な議論や学会活動等を通じて、UMN(アンメットメディカルニーズ)の解決に寄与、さらに高い倫理観が望まれます。こういった背景から日本製薬医学会では、MSLの資格要件として医学・薬学関連の大学教育を受けた者と提言していましたⅰ)。さらに2022年に日本製薬工業協会(製薬協)は、「MSLの目指すべき方向性」を発表し、その中でMSLの任命要件として、医療資格の保有(医師、歯科医師、薬剤師、看護師など)や、生命科学系の博士号の保有を推奨するとしましたⅱ)。これは、MSLが社外医科学専門家から真に信頼されるパートナーとして医学的・科学的な交流を行うにあたり、研究業績を挙げた経験を持つ科学者として博士であることがより望ましいと考えたと説明されています。 こういったハード面での要件の他に、高度な専門知識、 科学的中立思考、高い倫理観、科学的議論ができるコミュニケーションスキル、ビジネスに対する洞察力、自己研鑽への意欲などのソフトスキルも必要となってきます。

