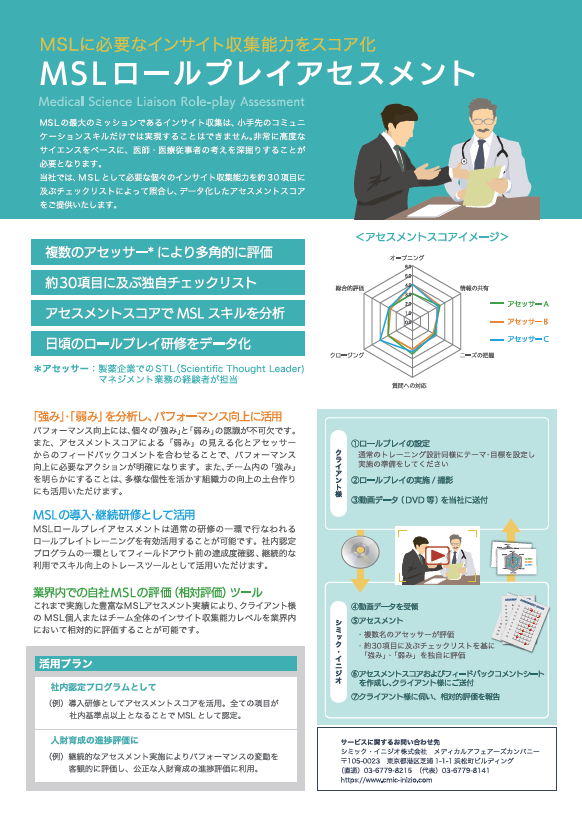MSLが気を付けるべき、研究の利益相反とは?
MSLの責務は、社外医科学専門家との科学的・医学的交流を通じて、医学の進歩および医療の発展に貢献することです。なかでも、現状のデータギャップを確認し合い、その解決策について議論することは、その後のエビデンス創出の貢献につながる重要な活動です。しかし、エビデンス創出に関する議論が、かえって研究の中立性を侵すものであってはなりません。研究の利益相反が厳しく問われる今、MSL業務の境界線を見極めることが求められています。本稿では、MSLの対外活動において気を付けるべき研究の利益相反について論じます。
エビデンス創出の担い手
メディカルアフェアーズ(MA)が掲げるミッションの1つに、「アンメットメディカルニーズの充足につながるエビデンス創出」(1)があります。MAは、アンメットメディカルニーズについて情報収集・分析するなかで、様々なデータギャップを拾い上げることとなります。そこには、自社製品に直接関わるものや、疾患全体に関わるものが含まれます。しかし、多数存在するデータギャップ(もしくはリサーチクエスチョン)を自社だけで解決しようとするのは非現実的です。社外の研究者が自発的に発案し、実施する臨床研究(「研究者主導臨床研究」と呼ばれます)によるエビデンス創出が重要な役割を果たすこととなります。製薬企業などの生命関連企業は、自社の関心領域(area of interest)と合致する研究計画に対して研究資金を提供するプログラムを用意していることが多いですが、実際、MAはこのプログラムに関与していることが多いでしょう。
産学連携と研究の利益相反
純粋な研究資金提供含め、営利企業とアカデミアが協働して研究することは、より良い研究成果の創出につながる可能性があります。一方で、営利企業は当然、自社の利益を考えた上で研究に関与しますので、利益相反管理が非常に重要になってきます。
利益相反(conflict of interest; COI)という用語は広く用いられますが、研究の利益相反は、「企業の研究への関与や、研究に関わる企業と研究者との間に経済的利益関係が存在することにより、研究で必要とされる公正かつ適正な判断が損なわれると第三者から懸念されかねない状態」(2)と説明されています。言うまでもなく、研究者には科学的公正に研究を実施する責務があります。ある研究者が特定の企業から経済的利益を受けている場合、その研究者は提供元の企業にとって有利になる研究成果を出すのではないかという懸念が生じます。利益相反自体は不正な状態ではなく、産学連携を進める上では避けられませんが、適切に管理されなければなりません。すなわち透明性を確保し、かつ不正が生じうる状況が生まれないよう対策を講じることが求められます。例えば共同研究においては、契約において具体的な役割分担が定められ、それが一定開示されることになります。データ管理や統計解析については第三者に委託するなどの対策も講じられます。
研究者主導臨床研究に対する指針
日本製薬工業協会(製薬協)は、研究者主導臨床研究を、企業からの委託研究や共同研究とは一線を画したものと位置付けています(3)。具体的には、「研究者主導臨床研究では、研究計画の企画・立案、実施、管理等において独立性が重要であることから、研究資金、市場調達が困難な技術、薬剤・医療機器等の提供・貸与を除き、製薬企業の関与は控えるべきである」という指針を策定しています。これに則るとすると、研究者主導臨床研究において、もし見えない形で企業に研究者に対して影響力を行使しているのであれば、それは好ましくない状態と言えます。
MSLと社外医科学専門家との交流の「見え方」
前置きが長くなりましたが、MSLが研究の利益相反とどのように関係するのか、これから述べていきます。
MSLの主な業務は、社外医科学専門家との医学的・科学的交流です(4)。その中で、自社製品のデータギャップは重要な論点になります。どのようなリサーチクエスチョンを立て、どのようにエビデンス構築を進めていくべきか、MSLは社外科学専門家とそのような議論ができるよう準備しておく必要があるでしょう。
しかしMSLは、営業組織から独立しているとはいえ、営利企業の一員です。他方、MSLが交流する社外医科学専門家は、講演料など自社から何らかしらの経済的利益を受けている場合が多いでしょう。それらを踏まえて乱暴な見方をすると、MSLと社外医科学専門家の関係性は、あくまで「営利企業の社員と、その企業から一定の報酬を受け取っている医師」との関係性と言えます。たとえ自分たちは科学的公正な振舞いをしていると考えていたとしても、外部からの「見え方」には配慮しなければなりません。
MSLは何に気を付ければよいのか?
前述した製薬協の指針では、研究者主導臨床研究に対して「研究者の独立性」や「研究結果/研究の中立性」に影響を与える支援をしないよう定められていますが(4)、それは当然、MSL活動にも適用されます。例えば、MSLが自社製品に有利となる研究成果を出してもらうよう研究者に働きかけることは、研究の中立性という観点から問題のある行動です。そのほか、どこにも開示されない隠れた形でプロトコル作成などの具体的な労務支援をすることも避けるべきでしょう。
研究成果は、公正に実施されて初めて学術的・社会的価値を持つことになります。過去の業界での過ちを踏まえ、研究者自身が利益相反を理解し、研究を実施するのは当然です。加えて、研究者と交流をするMSLも、利益相反を理解した上で、対外活動を実施しなければなりません。
弊社はクライアント企業から「MSLが、研究立案に関する議論にどこまで踏み込んでよいかわからず、悩んでいる」というご相談を受けることがあります。特に昨今、MAと営業・マーケティング部門との連携を強化しようという動きが強まっていますが、そうなるとMSLの科学的公正性が問われる場面が、さらに多くなることが想像されます。今後、環境の変化に応じて、MSLの行動基準を見直す、コンプライアンス研修を強化するなどをして、対応していくことが必要となるでしょう。
(1) 日本製薬工業協会:メディカルアフェアーズの活動に関する基本的考え方(2019年4月1日)
(2) 厚生労働省医政局研究開発政策課長通知:臨床研究法における臨床研究の利益相反管理について(医政研発0515第12号令和7年5月15日)
(3) 日本製薬工業協会:医療用医薬品等を用いた研究者主導臨床研究の支援に関する指針(2020年10月12日改定)
(4) 日本製薬工業協会:メディカル・サイエンス・リエゾンの活動に関する基本的考え方(2019年4月1日)